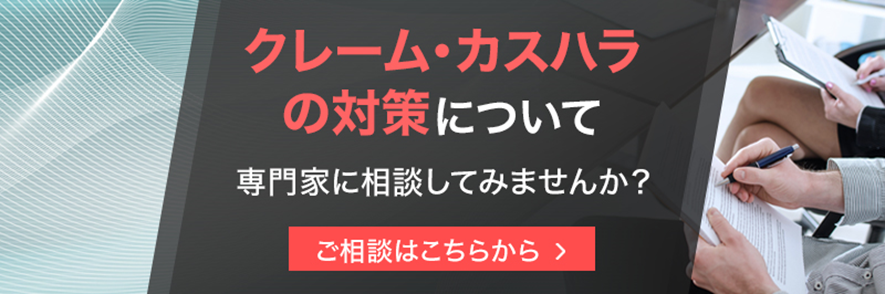使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説

悪質クレームやカスハラが社会的に注目されるようになってから、「対策マニュアルの作成が重要」との意見を耳目にすることが増えました。一方、悪質クレームに対しては以前から対策を講じようとしている会社組織も多く、「正当なクレームには誠実に対応し、悪質なクレームには毅然と対応する」といった方針が盛り込まれたマニュアルが作られて来ました。
近年でも、2022年2月には厚生労働省が『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』を公開していますし、2024年10月には東京都が公布した『東京都カスタマー・ハラスメント防止条例』の中でも、事業者による措置等として「カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成」が定められています。これらの動きは、クレームやカスハラの第一線で対応するスタッフにとっては、大上段に構えた条例や方針よりも、それらを踏まえて“具体的にどう対応したら良いか?”というアクションの提示が切実な問題であり、それが無ければ、目の前のトラブルへの対応には役に立たないからです。
クレームやカスハラへの対応は具体的な場面への対応の連続なので、「正当なクレームには誠実に対応し、悪質なクレームには毅然と対応する」といった単なるスローガンレベルの内容では、ほとんど役に立ちません。また、企業によって被害実態や必要な対策が異なるため、今から対策を始めようとする企業が既成のマニュアルをそのまま使うだけでは、なかなか上手く行かないのが現実です。
実際、厚生労働省の第3回『顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議(開催日:2021年7月26日)』では、議事要旨に下記の記載があります。
| (厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課) マニュアルは、主に想定しているのは飲食業界や小売業界等の企業向けのものだが、特定の業界に特化した内容にすることは考えていない。業界としてそのまま使えない場合は、今回作成するマニュアルを参考にして、特定の業界向けに作成するといった使い方をしていただければと考えている。 |
そこで本コラムでは、コールセンターの品質管理マネージャーとして3,000件以上のハードクレームやカスハラに対応し、様々な対策を講じ、実際にマニュアルを作成・運用して来た経験に基づいて、クレームやカスハラの対策マニュアルの活用に関し、大きく3つのポイントを解説いたします。
使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説
マニュアルを動かすためのマネジメントシステムを確立する
クレームやカスハラは、その場をやり過ごせれば良いというものではありません。その場はたまたまマニュアルそのままのクレームだったので何とかやり過ごせたとしても、ちょっとでも違ったシチュエーションだとコテンパンにやられるのでは、従業員・スタッフは悲惨ですし、企業にとってはリスクそのものです。また、クレームの真因を究明し、商品やサービスの改善に反映させたり、同種のカスハラが再発しないように対策を講じたりしなければ、問題の根本的な解決にはなりません。何よりも、そういった対応が組織の方針やルールに合致していなければ、散々怒鳴られながら何とか対応したとしても、組織としては何の成果にもならない、といったことにもなりかねません。
そこで重要になることは、経営も関与しながらマネジメントシステムを構築し、その中でマニュアルやトレーニングの運用をして行くことであり、「マニュアルではなく仕組みを作る」という発想の転換が重要です。
具体的には、まずは自社にどのようなリスクがあるのかしっかりとアセスメントすることから始めます。
リスクアセスメントの実施
自社にどのような顧客接点があり、どのようなやり取りが行われており、どのようなクレーム・カスハラのリスクがあるのかについてアセスメントを行い、必要な対策を検討します。
ポイントは、顧客接点毎にリスクの特定、リスクの分析、リスクの評価を分け、具体的に把握して行くことです。上記のステップをまとめて実施してしまうと、リスクを過少または過大に評価してしまったり、悪い場合には、そもそも顧客接点として認識されない可能性があります。また、事例や実際の対応例を踏まえて具体的に把握して行かないと、現場の顧客対応に役立たない、ふんわりとしたスローガンのような対策になってしまいかねないので、注意しましょう。
分析や評価をせず、まずは顧客接点毎のリスク特定に集中すれば、評価基準に当てはまらない事例のように感じたとしても、従業員・スタッフが困ったり嫌な想いをしたりしたことはスクリーニングせずに拾い上げることが可能です。そのうえで、リスクの分析や対策が不十分になっていないか注意深く検証して行けば良いでしょう。
体制の構築
リスクアセスメントに基づいて、誰が、どのような権限で、どのようなルールに基づいてマネジメントして行くかといった枠組みを決めて行きます。
体制構築のため決めるべき事項は、組織の規模、ビジネスモデル、成熟度などによって大きく異なりますが、これからクレームやカスハラに対するマネジメントシステムを構築するのであれば、例えば下記の3点が挙げられます。
責任者と推進メンバーを決定する
ハードクレームやカスハラは、原因・改善策ともに広範に及ぶことが多いため、社内の利害対立を俯瞰的に判断し組織として進むべき方向に導けるように、役員クラスを責任者に置くことをお勧めします。
また、役員の下で具体的に誰がお客様に相対するのかも決める必要があります。正社員や部課長など、本当の責任者が毎回対応していれば、当然ながら対応品質が高まります。しかし、対応コストが高額になりますし、本来業務が滞る可能性もあります。そのため、商材やビジネスモデルにもよりますが、一定の内容は一次対応スタッフが吸収することを目指し、そのためのバックアップ体制を検討するようにして行きます。
教育や評価などの制度と連携させる
クレームやカスハラに対応する可能性のあるスタッフには、必ず、必要な教育を受けさせ、必要最低限の能力は全員一律となるようにしましょう。そうしなければ、上司へのエスカレーションさえできなかったり、最悪の場合、自分では気付かないままクレームやカスハラを増やし続けてしまったり、といったことになりかねません。
また、クレームやカスハラへの対応は、営業目標達成などプラスのインパクトが無いので評価されにくいですが、組織にとっては重要な仕事です。そのため、対応スキル、意慾、周囲への影響、実際の対応状況などを組織として正しく評価してあげられるようにしましょう。
適正な報酬を与える
教育や評価だけでなく具体的な報酬も、商材、ビジネスモデル、組織特性などに応じて検討が必要です。
正社員中心で目標管理もしっかり機能している組織なら、目標に組み込むだけで良いかもしれません。しかし、小売り、飲食、コールセンターなど非正規雇用中心の労働集約型ビジネスでは、もっと多様かつ分かりやすい報酬が必要です。
なおこの“報酬”は、必ずしも金銭的な対価だけを指しません。その従業員の貢献度に触れながらちゃんとお礼を伝える、全体朝礼などの場で表彰する、閑散期にだけ使える特別有給休暇を付与する、といった取組みも全て“報酬”です。このような“報酬”は、人によって価値が変わるため、できるだけ多くの選択肢カードを持ちながら、相手や状況に応じ適切なカードを切れるようにしておきましょう。
クレームやカスハラへの対応方針を定め、効果的な対応フローをマニュアル化するためには、実態を反映したリスクアセスメントが不可欠です。しかし、社内でリスクアセスメントを行おうとしても、客観的に評価できず、過不足が生じてしまうことも少なくありません。ですから、今からクレームやカスハラへの対応体制を構築しようとする場合には、最初は専門家の支援を受けることをお勧めします。
もしお近くに信頼できる専門家がいない場合は、当社でも承っておりますので、ぜひ、お気軽にご相談ください。
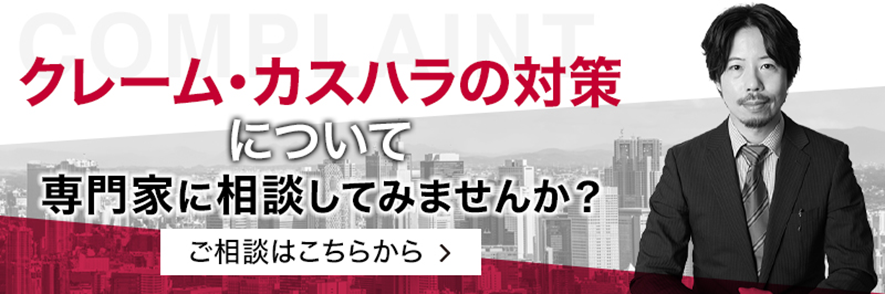
経営層によるモニタリングの実施
クレームやカスハラへの対応は、マニュアルを作ったり研修したりしたらそれで終わり、というものではありません。それらが正しく機能しているか、その結果として組織の方針や目的を達成しているか、環境の変化を踏まえて修正すべき点はないか、といった点を継続的にモニタリングする場を作りましょう。
件数が少なく、突発的に発生するような状況下では、発生の都度、経営会議や全社会議など幹部社員が揃う場で案件情報を共有し、評価、対応方針などについてのすり合わせを行っていくということでも良いでしょう。この場合のポイントは、必ず録画映像・録音音声・対応報告書などで、実際の顧客対応の状況を共有することです。例えば、単に「返品交換が2件あった」など数字でしか見ていなければ、「それくらいは必要経費と見るか」となる場合でも、実際にお客様が怒鳴り散らしながら交換を要求している録画データを見て、その従業員・スタッフが事後に退職してしまったといったことを把握したら、迫真性が増し、従業員が安心・安全に働き活躍してもらうため、抜本的な対策が必要だと理解されることも多いです。
また、クレーマーやカスハラが一定の頻度・件数で継続的に発生する場合には、定点観測するための会議体を作ることをお勧めします。会議体では、件数、案件カテゴリ、案件レベル、地域、客層、現在のステータスなどの傾向を共有します。そして、例えば上半期の傾向が前年同時期と同じであれば、前年効果的だった対策を前倒しで実施し、新種のクレームが発生していたら、原因を究明し、対策や再発防止策に繋げるといった、組織的な対策に繋げて行くことが重要です。
ボトムアップによるコントロール
経営陣によるモニタリングは重要ですが、クレームやカスハラは突発的に発生するため、その都度経営にお伺いを立てていたら対応が硬直的になってしまい、かえって炎上させることになりかねません。そのため、少なくても一次対応については現場で臨機応変に対応し、数字至上主義にならないように気を付けながら、必要に応じ柔軟に運用を改善して行く必要があります。
例えば、今でも一部の組織では、「クレームやカスハラは起こしてしまった現場が悪い」といった先入観を持っている人がいる場合があります。ですから、そういった組織で極端な件数目標を決めたりそれを評価と連動させたりすると、接客現場が改善活動よりも粗探しのようになってしまい、最悪の場合、隠ぺいの遠因になりかねないことに注意が必要です。そうならないようにするためには、最初の頃は特に、数値目標にこだわり過ぎずに(もちろん重要ではありますが)、定められたルールやアクションが適切に実行されたか、▲時間以内に必要な範囲に情報が共有されたか、教育の実施率や回答の正答率はどうだったかなど、やるべきことがやれていたかどうかにフォーカスし、やれていなかったならその原因を除去するための対策を取るといった対応を丁寧に続けて行きましょう。
また、クレームやカスハラへの対処に追われるだけでなく、常に商品やサービスに対する改善の視点を持つことも重要です。ただ、そうは言っても、クレームやカスハラのお客様から建設的な改善意見(VOC:Voice Of Customer)を聴取できることはそう多くはありません。そのため、現場の業務を熟知しており、実際にお客様と対応している従業員・スタッフから定期的に改善意見を集め、VOA:Voice Of Agentとして社内に共有し、改善を進めて行くことをお勧めします。
ポイントは、現場で臨機応変に対応し必要な改善活動を行うため、必要な権限を委譲し、能力を習得させるための教育を行うことです。経営によるモニタリングと並行し、ボトムアップにより改善して行きましょう。
具体的なマニュアルを作成し、クレームやカスハラに対する従業員の知識を向上させる
前段で説明した通り、「正当なクレームには誠実に対応し、悪質なクレームには毅然と対応する」といったスローガンレベルのものでは、現場で実際にクレーマーやカスハラと対峙している従業員・スタッフにとっては、ほとんど役に立ちません。
そのため、上記のリスクアセスメントで把握した具体的な顧客接点と、それに基づいた具体的なリスクを踏まえて、一次対応者としてどのような対応が必要かを検討し、フロー、基準、トークスクリプトや作業手順などのマニュアルにまとめて行きます。この時、「しつこく要求」「長時間の拘束」といったよく使われる文言は、「これ以上同じ内容は案内しかねることを伝えた後に2回以上要求」や「2回目の退出依頼から15分以上」など、極力、数字で判断できる基準にしましょう。曖昧な基準では、ハードクレームやカスハラなどのプレッシャーの大きな場面において、「これは“しつこい要求”になるのだろうか」と躊躇して長時間の罵倒を受け続けることになったり、反対に、自社のミスに気付かず案内に納得してもらえないからというだけで「“しつこい”要求だ」と判断し、不適切な拒絶をしてしまったりしかねません。
注意点は、一次対応者が迷わず判断できるように基準の数値化を心掛けるとともに、必ず、その判断が適切か否かを組織的に判断するプロセスを持たせることです。そうすることにより、今回の案件がその基準やフローに当てはめるべき案件か、対応に過不足が無いかなどを適切に判断し、真に排除すべき不当クレームやカスハラを排除できる可能性が高まります。
また、接客業務に追われるスタッフが参照するマニュアルであることを踏まえるなら、一つ一つのコンテンツは朝礼などで読み合わせられる程度のボリュームにし、いざクレームやカスハラが発生した時にも迅速に検索できるように索引や目次をつけるといった工夫も必要不可欠です。
なお、「対策マニュアル」と聞くといわゆる業務手順書のようなイメージを持つ方がいますが、それだけに限りません。業務特性に応じて以下のようなドキュメントを組み合わせながら、具体的な案件に対し実効性を高めて行きましょう。
業務手順書
主に業務のやり方そのものを解説したマニュアルです。対面であれば、監視カメラの位置、立ち位置、クレームやカスハラの判断基準、確認内容、案内事項、事後処理などを案内ベースで解説します。また、専用システムを使う場合は、その操作方法や対応履歴の残し方についても記載しておきましょう。
トークスクリプト
クレームやカスハラの対応において、シチュエーション別の案内事項を、そのまま読んで使える台本形式にして共有します。この時、1問1答のようなカウンタートーク集でも良いですが、頻出のシチュエーションについては、以下のように実際の顧客対応の流れが分かるようにしておくと良いです。
参考例:商品交換不可が不承につき、上司への交代を要求された場合
各種フロー図
画面遷移、業務の進み方、関連部門との連携、エスカレーションの流れなど、フロー図にした方がぱっと見で分かりやすくなる情報は、できるだけフロー図にしましょう。全てをフロー図にするのは大変ですが、咄嗟のクレームやカスハラでは分厚いマニュアルを読み解いている時間はないので、参照頻度の高い箇所や迷い易い箇所から優先的にフロー図を作りましょう。
チェックリスト
例えば、一次対応で最低限確認しなければいけない情報、クレームやカスハラに特有の後処理で忘れがちなことなどは、マニュアルとは別にチェックリストを用意しておくと良いです。
関係者の連絡網
そもそも連絡先を知らなければ、いざという時に連絡が着かず役に立ちません。しかし、役員や管理職の連絡先までズラっと並んだ連絡網があっても、遠慮して誰もそこに連絡しなければ無用の長物です。
連絡先を掲載するとともに、連絡基準、その時の件名、担当者や責任者の確認サイクルなども定め、有事の際に活用できる連絡網を作りましょう。
教育やトレーニングにより、クレームやカスハラへの対応スキルを身に着ける
ハードクレームやカスハラへの対応においては、マニュアルを配布するだけでは全く不十分です。激怒して怒鳴り散らすお客様や理詰めで厳しく追及して来るお客様に、十分な反論材料も無いまま執拗に謝罪や補償を要求されるプレッシャーは想像を絶するものがあり、発生してから冷静にマニュアルを調べその通りに体制することは不可能です。そのようなシチュエーションに対応できるようにするためには、具体例に基づいたマニュアルを作成するとともに、具体例に基づいたロープレ(ロールプレイング)を事前に行うことで、実際の対応の流れを体験させ、対応を“予め身に付けておく”ことが有効です。
ただ、そうはいっても、実際にロープレをやるとなれば、シチュエーションの確認、セリフの共有、ロープレの実施、フィードバック、修正点の共有などやることは盛り沢山であり、5分程度のロープレであっても前後を含めると30分近くかかることも珍しくありません。1人ではできず、最低2人以上の人員がいなければ成立しないため、現場への負荷が大きいことも軽視できません。そのため、接客業務に追われる小売店や飲食店の現場においては、定期的な集合研修でロープレを行うことは困難を極めます。そういった状況に対しお勧めなのは、ロープレの様子を短い動画マニュアルにし、いつでもどこからでも参照できるように社内イントラで共有する事です。
近年は、株式会社スタディストのTeach me Bizなど、非常に使い勝手の良い動画マニュアル作成ツールもあります。そういったツールを導入するほどのコンテンツボリュームが想定できないなら、まずは、Microsoft StreamやYouTubeで動画を共有しても良いでしょう。朝礼や夕礼の時に皆で参照し、お客様とスタッフに分かれて簡単に練習をしてみたり、閑散時間帯に現場から一人ずつ抜いてショート動画を見せ、感想を聞いたり、といった対応をして行くだけでも良いです。テキストだけのマニュアルと違い、動画の場合は対応イメージやポイントが分かりやすく伝わるので、非常に効果的です。
まとめ
クレーマーやカスハラへの対策としてマニュアルの重要性はよく耳にしますが、真に重要なことは、単にマニュアルを作るだけでなく、どのようなリスクに対応しどのように運用するかといった枠組みを明確にし、そこに合わせてマニュアルを作成し、作ったマニュアルを組織に浸透させることです。また、そういった取組みを成功させるためには、対策の初期段階でリスクアセスメントを実施し、自社にどのようなクレームやカスハラのリスクがあるのか具体的に理解することが欠かせません。リスクについて具体的に理解したうえで、そのリスクを軽減させるための対策を講じ、その対策をマニュアル類に反映させていきます。
上記の様な取組みについて、専門家に相談してみたいという方や、現在もクレームやカスハラが継続的に発生していて対策に苦慮しているという方は、ぜひお気軽にご相談ください。