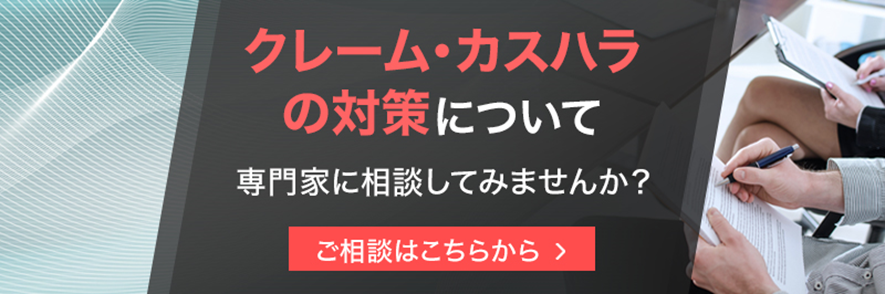カスハラ対策は弁護士に任せればOK? いえ、自社対応と弁護士は両輪です

悪質なクレームやカスハラへの対応について簡単なアドバイスをすると、時折、
「ProClaimさんにお願いできるなら安心です」や
「我々民間人は、暴力的・威圧的なクレームやカスハラに対応はできないので、よろしくお願いします」など、
丸投げを前提にお話しをされる方がいます。
また、そうではなかったとしても、
「うちは顧問弁護士がいるし、トラブル起きたら全部任せるから大丈夫」など、
結局丸投げ先が違うだけといったことも少なくありません。
確かに、いかに責任ある立場の方であっても、仕事でやっていることに対して暴力的・威圧的な態度で延々と無理な要求を突き付けられ、酷い時には休日にまで呼び付けられたり家族にまで暴言を吐かれたりといったことがあれば、それ以上対応をしたくない、と思ったとしても理解できないことではありません。
ですが、昨今はカスハラに対する社会的注目度が高まったからか、コンサルタントや専門家を名乗る人が増えていますが、そもそもカスハラへの代理交渉をコンサルタントが受託することは、弁護士法72条の非弁活動(簡単に説明すると、「弁護士以外の人が法律上のトラブル解決を業として請け負ってはいけない」という決まり)に抵触する可能性があります。ですから、まともなコンサルタントなら代理交渉をそのまま受託することはありえませんし、甘言を弄して受託しようとするコンサルタントには細心の注意が必要です。
弁護士への依頼についても、丸投げできるから安心という訳ではありません。端的に言えば、弁護士が絶対的に必要な場面は裁判所に対する手続きが必要な場面であって、仮にトラブルの芽はあったとしても、その全てをいちいち弁護士に相談していたら仕事が進まなくなってしまいますし、コスト的にも大変な負担です。また、弁護士は法律面からの助言や提案はしてくれますが、法律面だけでなく営業面や人事面も含めた経営判断をしてくれる訳ではありません。つまり、一定ラインを超えたトラブルは弁護士への移管が避けられないとしても、そのラインまでは原則として自社対応が避けられず、また、自社で対応するべきです。
そこで今回は、自社で対応すべきこと、弁護士への依頼を検討すべき境界線、弁護士に依頼する際の注意点などについて、分かりやすく解説いたします。
カスハラ対策は弁護士に任せればOK? いえ、自社対応と弁護士は両輪です
クレームやカスハラについての弁護士への相談例
最も重要なことは、正当なクレームでも、悪質なクレームでも、カスハラでも、提供する商品やサービスに差をつけないこと。つまり、そのお客様が何をして来たとしても、それによって譲歩や優遇をしたりせず、他のお客様と同様の対応をすることです。ですから、それで商品やサービスの提供自体は公平に行えるのであれば、クレームやカスハラには積極的に対応せず、受け流して何もしないことも立派な対応です。
当社がコンサルティングしているクレーム・カスハラのマネジメントシステムは、上記のような公平な対応を自社主導で実現するための仕組み作りです。しかし、残念ながらどのようなマネジメントシステムを構築しても、100%完璧ということはありえず、どこかで必ずトラブルが発生します。そのトラブルが以下のような例に該当し、法的な手続きをとるのが最良と判断する場合には、弁護士に移管への相談をお勧めします。
行為を禁止する(例:来店禁止の仮処分など)
名誉棄損や営業妨害などは、自社にとっては深刻な迷惑行為ですが、訴訟を起こしたり警察に被害届を出したりしても決着に1年以上かかることは珍しくありません。しかし、決着まで何度も来店し、長時間窓口を占有して文句をつけられては、企業の被害も拡大しますし、対応できたはずの他のお客様にとっても迷惑千万です。
そのような場合には、相手の行為を禁ずる仮処分の申立て等ができないか相談しましょう。
行為を実行させる(例:損害賠償の請求や差押えを求める場合など)
例え悪質クレームやカスハラによって自社に被害が出ていたとしても、こちらが算定した被害額を無条件に受け取れる、という訳ではありません。行為の禁止と同様、強制的に実行させる場合には、訴訟を通じた債務名義の確定や、請求や差押えについて等、弁護士に相談しましょう。
示談する(係争前、係争後、ともに)
前2例のような裁判上の手続き前に合意できる場合、手続き後に合意できる場合、いずれの場合でも示談する時には必ず示談書を取り交します。その際は必ず、クレームやカスハラの内容、示談内容、示談書の文面、法的な評価などについて、事前に弁護士に相談しましょう。
なお、係争前の示談の場合、つい示談書のやり取りを軽視してしまうことがありますが、示談交渉をしたのであれば、本当に示談書が不要な状況かなどについても弁護士に相談すると良いです。
警告する
トラブルの内容によっては、弁護士に法的措置等の警告を相談しましょう。
ちなみに、「今後同様の対応をされた場合は法的措置を取ります」といった警告であれば自社でもできますが、弁護士名義での警告の場合、既に弁護士に経緯が共有されており、いつでも引き金がひける状態だということが伝わるので、多くのクレームやカスハラはこの段階で止まります。また、もし止まらなかったとしても、そのまま弁護士に対応を移管し手離れできることは大きなメリットです。
交渉そのものを依頼する
上記と同様、トラブルの内容によっては交渉そのものを弁護士に移管することも一法です。
具体例としては、不利な念書を差し入れてしまった、取引先に執拗なクレームを入れられている、相手に反社の可能性がある、といった場合には、一刻も早く弁護士に相談すべきです。
また、上記の様に緊急性は無くても、クレームやカスハラの原因がこちらにもあり、一定の補償は避けられないといった場合は、弁護士に交渉を移管することで、裁判になった場合の見通しや労力を踏まえながら、現実的な落としどころを探すことができます。
上記で全てとは限りませんが、前述の通り、弁護士への相談や依頼は概ね、トラブルが一定レベルに達した『後』の話しであり、そこに至る『前』は基本的に自社対応になるというイメージが掴めたと思います。
クレームやカスハラへの対応を弁護士にスムーズに移管し、その後の対応を有利に進めるためには、この、移管する『前』の自社対応が極めて重要です。特に、交渉そのものの移管のような、これから対応が本格的に始まって行くという場合には、普段からの組織的なマネジメントシステムが大きく影響します。また、そういった組織的なマネジメントシステムを構築することは、普段から不当クレームやカスハラを防衛することになり、従業員満足度と顧客満足度の両方を高める事に繋がります。
クレームやカスハラに対するマネジメントシステム構築について、専門家にご相談を希望の方は、お気軽にご連絡下さい。
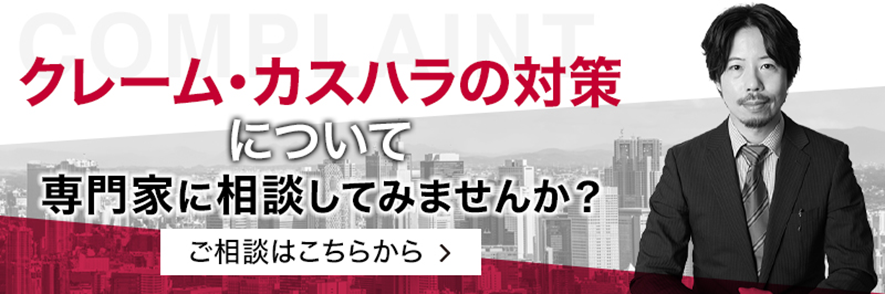
弁護士への相談を見越して自社で対応すべきこと
弁護士への移管の『前』に、普段から社内でやっておいた方が良いと思われることを具体的に見て行きましょう。
以下のような対応を組織的に行うことで、普段から対応が一貫し、不適切な対応をするリスクが軽減し、有事の際にも弁護士に対し経緯を正確に引き継ぐことができるようになります。
対応方針やガイドラインの作成
社内外に対し明示し、組織がそれに沿って統一的に対応するような方針やガイドラインを作成します。
こういった対応方針やガイドラインが無いと、案件毎、担当者毎で対応にバラツキが発生し、場合によっては不適切な対応をしてしまうこともありえます。普段からそのようなことが無いように、基本的な対応方針を明文化しておきます。
規程やマニュアルの整備
規程やマニュアルなどの業務文書を整備することで、顧客対応をする全スタッフの対応を平準化して行きます。
なおこの「マニュアル化」については、いわゆる業務手順書のようなものだけに留まりません。トークスクリプト、業務フロー図、チェックリスト、連絡網など、想定されるクレームやカスハラの内容に応じてドキュメントを整備しましょう。
従業員への教育
マニュアルを作成しただけでは、強いプレッシャーのかかるクレームやカスハラへの対応の場面で、そのまま対応できる訳ではありません。実際のクレームやカスハラの例を元にしたロールプレイングをするなどし、マニュアルの知識をスキルとして定着させましょう。
顧客向けの文書の見直し
内部向けのマニュアル化だけでなく、これらお客様が接するチラシやポスター、契約書や説明書、その他の情報にもクレームやカスハラのリスクが無いか、クレームやカスハラへの対策と矛盾が無いかなどを確認し、必要に応じて見直しをかけて行きましょう。
対応記録の蓄積
顧客対応の経緯は必ず、時系列で記録しておけるようにしましょう。電話や来店の他にも、メール、訪問や来社、郵便など、時間の経過とともにチャネルが拡大していくこともありますが、それらも一元的に参照できるようにしておきます。
相談体制の整備
厚労省カスハラ対策マニュアルでは、相談体制として、「対応者のエスカレーション先確保」と「メンタルヘルス対策」の必要性が強調されています。
これらを社外に置く場合は、機密情報や機微情報として、現場の顧客対応と切り離されている場合が少なくありません。そのため、弁護士に対応を依頼する場合には、これら外部の相談先からも必要に応じ情報共有してもらえるようにしておきましょう(例:途中で行った法務相談の内容や、クレーム・カスハラの影響で従業員がメンタルヘルス不調になったのであればその状況など)
対策だけでなく、クレームやカスハラの予防のためにも、弁護士は力強い味方になる
上記の様な対応を取ることで、いざ弁護士に対応を依頼するとなった場合にも、自社の対応方針や業務フロー、それらを踏まえてなぜクレームやカスハラが発生したか、それに対しどのように対応して来たか、といったことを正確に引き継ぐことができます。
しかし、実は自社の対応プロセスの中に平時から弁護士の専門知識を取り入れることで、些細なトラブルが悪質クレームやカスハラになる可能性を下げることも可能です。
例えば、以下のような対応が挙げられます。
- リスクアセスメントへの参加
社内にどんな顧客接点があり、どんなクレームやカスハラのリスクがあるか、毎期一定のタイミングや経営環境が大きく変わったタイミングで評価を行います。この時、弁護士にも参加してもらい、法的観点からリスク評価について意見をもらいます。 - リーガルチェックの実施
業務フロー、各種マニュアル類、チラシやポスターなどの掲示物、契約書や説明書などの配布物、といった各種ドキュメント類に関し、法的視点から事前にリスクのチェックをしてもらいます。 - 定期的なアドバイス
マネジメントシステムの中で、例えば弁護士にも会議体に参加してもらい、法的観点からコメントをしてもらうことで、トラブルの芽が芽のうちに摘むようにします。
弁護士に依頼する時の注意点
これまで、クレームやカスハラへの対応を弁護士に依頼することの有効性を解説して来ましたが、弁護士に依頼すれば必ず終息するという訳ではありません。
弁護士に交渉を依頼することでかえって態度の硬化を招いたり、「弁護士から圧力をかけられた」といった内容をWEB上で喧伝されてしまったら、それこそ訴訟も避けられない事態になりかねません。それでも「訴訟で白黒ハッキリ着くから良し」とするなら良いでしょうが、クレームやカスハラが止み損害が回復されるのであれば、時間、費用、労力、その他のあらゆる面から見て和解が有利であり、和解できる可能性が十分にあるのにそれを積極的に放棄し、訴訟を選択する必要は無いはずです。
このような観点から、弁護士に依頼する際の最低限の注意点を共有します。
- やり取りを正確に、包み隠さずに共有する
対応が長期間にわたっていたり、登場人物が多かったり、メールの場合などラリーの数が膨大になっていたりする場合には、やり取りの生データを共有するだけでは経緯の把握に長時間を要したり、場合によっては誤認されてしまったりする場合もあります。そのため、情報量が多い場合には、一定の範囲で時系列や要旨をまとめたりすることで、弁護士が速やかに正確に事態を把握できるようにしましょう。 - 規程、マニュアル、教育内容などの関連する社内文書も共有する
特に、自社の側にも一定の落ち度がある場合は、トラブルの発生経緯や組織的な責任・対策の適否についての判断材料として、社内文書の共有は重要です。 - 丸投げせず、必ず、対応方針をすり合わせる
上記と同様でこちらにも一定の落ち度がある場合や、表面的なゴールと本音のゴールが違っている場合などは、必ず、その内容と落としどころを事前にすり合わせます。また、上記の様な事情が無い場合でも、弁護士に対応を依頼した直後からクレームやカスハラが全面的に止む訳ではありません。相手によっては「代理人など認めない」としつこく文句を言って来る場合もあります。ですから、ゴールイメージ、そこまでのロードマップ、交渉のスタンス、直近のアクション、代理人ではなく自社への連絡が続く場合の対応などについては、必ずすり合わせをしておきましょう。
最後に
自社のマネジメントシステム構築と、弁護士への依頼は、悪質クレームやカスハラへの対応における両輪です。自社内にマネジメントシステムを構築すればそれで絶対に大丈夫という訳ではなく、同時に、弁護士に丸投げすれば済むという訳でもありません。両者の目的や特性をよく理解するとともに、自社のクレームやカスハラ、経営環境などの特性も理解し、柔軟に対応して運用して行きましょう。
なお、これから対策をして行こうという企業の場合は、まずはマネジメントシステムを構築することを強くお勧めします。理由は、効果的なマネジメントシステムを構築できればクレームやカスハラの数が減るので弁護士に依頼が必要な案件も減ること、マネジメントシステムの構築はクレームやカスハラの対策だけでなく従業員満足度や顧客満足度の向上にもつながること、そして、マネジメントシステムの構築は従業員の育成やモチベーション向上にも繋がることです。その中で、必要に応じて弁護士にも相談して行けば良いでしょう。
自社での対応について専門家にご相談を希望の方は、お気軽に下記からご連絡下さい。