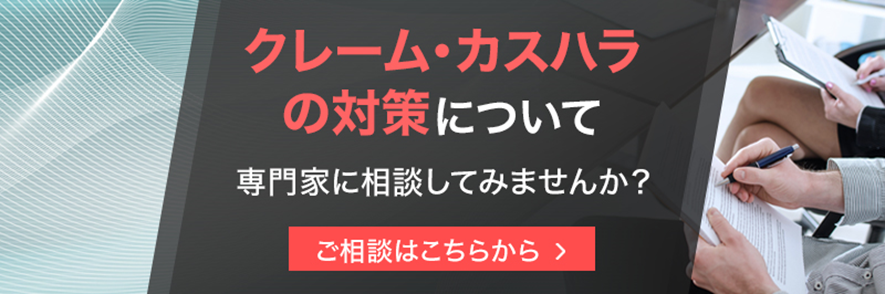【カスハラとは?】事例に基づいた具体的な基準と、対応のポイントを解説

以前は、いわゆる反社会的勢力による不当要求の場合、それと分かる肩書のついた名刺を提示されたりするので、一目で悪質か否かの見分けがついていました。
しかし現代は、悪質なクレーマーやカスハラユーザーは、「悪質クレーマー」「カスハラユーザー」という名札をつけて来てくれる訳ではありません。初期段階では、商品やサービスの何らかの不備に対する苦情として現れることが多いです。そのため、服装、態度、肩書などの外形的な情報だけで、そのお客様が「悪質クレーマー」や「カスハラユーザー」になるかどうかの判断をするのは難しくなりました。
自社の商品やサービスに不備があったなら、程度の大小はあっても、企業に不満や反感を持ったり、それを伝える時にも感情的になったりしても不思議ではありませんし、その理由を正確に説明できるお客様ばかりでもありません。ですから、特に対応の初期段階においては、外形的にお客様がお怒りだったとしても、その背景や理由を丁寧に確認し原因を解消する努力をせずに、「馬鹿野郎と言われたから」「こちらが説明してもいつまでも納得しないから」といった外形的な理由だけで悪質クレーマーやカスハラユーザー扱いをしていたら、そうではないお客様まで失ってしまうことになりかねません。
重要なことは、どの時点で、どうやって悪質クレーマーやカスハラユーザーと判断したら良いか、ということです。それに対し明確な基準を持たず、「カスハラには毅然とした対応」などとキャッチフレーズだけを掲げても、そもそも毅然と対応すべき対象を見分けられない、ということになりかねません。
そこで今回は、悪質クレームと比較しながらカスハラの公的な判断基準を確認し、分かり難い部分を具体的に解説するとともに、グレーゾーン対応の注意ポイントについてもお伝えします。
【カスハラとは?】事例に基づいた具体的な基準と、対応のポイントを解説
「クレーム」と「カスハラ」の違い
クレームとカスハラは混同されることが多いですが、大前提としてカスハラはパワハラやセクハラなどと同じくハラスメントの一種であり、クレームの延長ではありません。
「クレーム」は企業や組織の定義であり、自社で自由に基準を設定することが可能です。ですから、それぞれの企業が「当社は、内容に関わらずお客様が怒鳴られたらクレームとします」「当社は、お客様の態度と無関係に自社のミスを指摘されたらクレームとします」など独自に基準を設定し、対応を決めることができます。
しかし、「カスハラ」はパワハラやセクハラなどと同じくハラスメントの一種であり、企業自身も規制を受ける側なので、まずは公的な基準を理解することが重要です。
2025年1月現在、まだカスハラを定義する法律はありませんが、2022年2月には厚生労働省がカスハラ対策企業マニュアルを公開しており、2024年10月には東京都でカスタマー・ハラスメント防止条例が可決されました。他の自治体でもカスハラに関連する条例の可決が続いていますが、まずは先行する上記の2つの基準を確認しましょう。
厚生労働省『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』におけるカスハラの定義
厚生労働省(国)の対策企業マニュアルでは、以下の通り定義されています。
| 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの ■「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例 ・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合 ・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合 ■「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例 (要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの) ・身体的な攻撃(暴行、傷害) ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言) ・威圧的な言動 ・土下座の要求 ・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動 ・拘束的な行動(不対処、居座り、監禁) ・差別的な言動 ・性的な言動 ・従業員個人への攻撃、要求 (要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの) ・商品交換の要求 ・金銭補償の要求 ・謝罪の要求(土下座を除く) |
東京都『カスタマー・ハラスメント防止条例』におけるカスハラの定義
東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例では、以下の通り定義されています。
| (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 四 著しい迷惑行為 暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいう。 五 カスタマー・ハラスメント 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。 |
「カスハラの定義を企業が決める」にはリスクがある
厚労省のカスハラ対策企業マニュアルにおける「手段・態様が社会通念上不相当」については、上記の定義の通り刑事罰の対象になるような行為が具体的に列挙されており、判断に迷うことは少ないと思います。しかし、「要求の内容が妥当性を欠く場合」については、例示はされていますが、実際の顧客対応シーンに当てはめると具体性を欠き、判断が難しいとの声をよく聞きます。
これに対し、対策本などの中には、
「カスハラの定義は自社で決めて良い」
「カスハラと判断をしたら、対応を打ち切ってもOK」
といった意味の解説をしているものもありますが、これについては全く推奨できません。
まず、前述の通りクレームなら自社で定義を決められますが、カスハラは都や国(厚生労働省)が一定の定義を公開しているので、その内容が基準であり、「怒鳴られたから」「なかなか納得してくれないから」などといった理由だけでは該当しない可能性があります。にも拘わらず、例えば既に料金を受領していたり、契約期間中であったりする中で、自社が独自に設定した「カスハラの基準」に当てはまるからといって、対応を打ち切ったりしたら、乱暴な対応だと大きく喧伝されたり、内容や金額によっては契約不履行として損害賠償請求を起こされてしまうことも考えられます。
カスハラを定義する際には、必ず、自社で過去に発生した実際のトラブルや具体的な業務に当てはめながら、従業員やスタッフが直面する顧客対応においてなるべく迷わないものにして行くことが重要であり、そのようなプロセスを経なければ、現場と乖離した画餅になってしまう可能性があります。また、実際にやってみると、程度の軽重や内容の複雑性など複数のバリエーションがあり、かえって基準が分かり難くなったり、些細なトラブルまでカスハラ扱いして顧客満足度を低下させてしまったりといったこともありえます。そのため、カスハラ対策をこれから始めようという場合には、特に定義付けや対策の基本方針策定の段階では、専門家の助言を得ながら進めて行くことをお勧めします。
もしお近くにクレーム・カスハラへの対策や、顧客満足に対する専門家がいない場合は、当社でも承っておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。
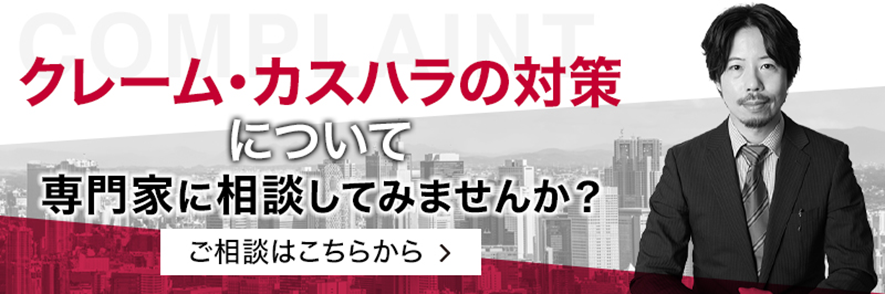
具体的な判断基準
前述の通り、いわゆる言動については、厚労省カスハラ対策企業マニュアルでカスハラに該当する具体例が列挙されており、東京都カスハラ防止条例でも「暴行、脅迫その他の違法な行為」「暴言その他の不当な行為」とやはり具体例が明示されていることから、判断そのものを迷うことは少ないはずです。
しかし、内容面については、東京都カスハラ防止条例では「正当な理由がない過度な要求」、厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルでも「要求の内容が妥当性を欠く場合」と書くにとどまっており、個々の顧客対応に適用させようとしても、そのままでは、これは正当な理由がないと言えるのか? これは要求内容が妥当性を欠くのか? と迷うことになりかねません。そのため、実際のカスハラ対応を成功させるためには、まず、上記の基準を具体化して行くことが重要です。
「企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない」の具体的な判断基準
厚労省のカスハラ対策企業マニュアルでは、「要求の内容が妥当性を欠く場合」の内容の一例として「企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない」と書かれています。
これを具体化するなら、以下の4つのパターンに整理できます。
商品・サービスに欠陥が無い
欠陥とは、通常有すべき安全性を欠いている状態です。例えば車の場合、出荷時点からブレーキが壊れている状態が該当します。
商品・サービスに瑕疵が無い
過失とは、欠陥とは言えないまでも、通常有すべき機能を欠いている状態です。例えば車の場合、新車を買ったのに納車時点で大きな傷がついていた、といったことが該当します。
商品・サービスに過失が無い
過失とは、損害に対する注意義務違反があることです。例えば車の場合、出荷時点ではブレーキが問題無かったとしても、1か月程度で壊れる事例が多数報告されていたにも関わらず特に確認や対策を取らなかった、といったことが該当します。
契約不履行が無い
契約不履行は、欠陥、瑕疵、過失などが無かったとしても、契約で「やる」と定められたことが実施されていない状態のことです。例えば車の場合、オプション追加の契約をしたのに、納車された車にそのオプションがついていなかった、といったことが該当します。
「要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合」の具体的な判断基準
厚労省のカスハラ対策企業マニュアルでは、「要求の内容が妥当性を欠く場合」の内容の一例として、上記に加えて「要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合」と書かれています。
これも、以下の3つのパターンに整理できます。
損害が発生して無い
自社に欠陥、瑕疵、過失、契約不履行などがあったとしても、それによる損害が発生していない場合を指します。例えば車なら、オプションを付け忘れたけれど、納車直後に自ら付け忘れに気付き、お客様からご指摘される前に取り付けたなら、損害が発生しているとは言えません。
原因と損害に因果関係が無い
損害が発生していたとしても、その原因との間に相当な因果関係が無い場合を指します。例えば車なら、オプションの付け忘れという瑕疵によりその日は運転ができず、出席予定だった会議でウン千万円の商談ができなかったからといった損失補填を要求されたとしても、通常、そのような商談も取引金額も成否も事前に予測するのは困難であり、因果関係が認められません。
損害の回復と要求内容に因果関係が無い
損害が発生していたとしても、その損害と自社の欠陥、瑕疵、過失、契約不履行などに、因果関係が無い場合を指します。例えば車なら、上記のオプションを付け忘れたことに対し別な新車への交換を要求されるといったことが該当します。この場合、オプション取り付けに関わる工賃や出張代金、場合によっては、代車費用などのお客様に生じたコストも企業が負担すべきでしょうが、別な新車への交換はオプションの付け忘れと因果関係がありません。
対応のポイント
上記の7つのパターンに該当する場合、自社が負うべき合理的な責任が無いことになります。そのため、基本的な対応方針は、事実関係を丁寧に説明し、誤解がるならそれを解き、可能な範囲で代替案を提示して行くことになります。
また、上記の様な対応をしても一向に納得せず、無償交換や返金、経営層による謝罪などの理不尽な要求を執拗に要求し続けて来る場合には、悪質クレームやカスハラに該当する可能性が大となります。その場合は、自社でできる対応を提示しながら、最終的にはお引き取りいただくのが妥当です。
参考:カスハラ対応事例 |確実に撃退するため、交渉打ち切りの5ステップ
なお、上記の判断基準、判断のポイント、対応例をまとめると、下表のようになります。
実際に自社でマニュアルやチェックリストを作成する場合には、この表の「判断のポイント」に自社の具体的情報を当てはめながら「対応例」を検討して行くと、漏れが生じにくく、かつ、現場でも判断しやすい“使える”マニュアルになるので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
| 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 | 厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアル | 判断のポイント | 対応例 | |
|---|---|---|---|---|
| 正当な理由がない過度な要求 | 要求の内容が妥当性を欠く場合 | 企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない | 商品に欠陥が無い (欠陥=通常有すべき安全性を欠く) | 上記を丁寧に説明し、企業として可能な代替案を提示するが、それで納得せず要求をひたすらゴリ押しする場合は、カスハラの可能性が高い。 |
| 商品に瑕疵が無い (瑕疵=通常有すべき機能を欠く) | ||||
| 契約不履行が無その他の過失が無い (過失=損害に対し注意義務違反がある) | ||||
| 契約不履行が無い (「やる」と約したことをやって無い) | ||||
| 要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合 | 損害が発生して無い | 相応のお詫びをし、ご納得いただく。損害が発生していないので、それ以上の対応には応じない。 | ||
| 原因と損害に因果関係が無い | 相応のお詫びをするが、因果関係のあることにしか(例:直接損害に対する補償)応じられないことを丁重に説明する。 | |||
| 損害の回復と要求内容に因果関係が無い | ||||
| 暴行、脅迫その他の違法な行為 | 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動 | 要求内容の妥当性に関わらず不相当とされる可能性が高いもの | 刑事罰の可能性が高い言動 | 暴行、傷害、脅迫、名誉棄損、侮辱、強要(土下座等)、不退去、監禁、性的言動 |
| 暴言その他の不当な行為 | 要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの | 不当要求の可能性が高い言動 | 金銭要求、商品交換要求、執拗で継続的な言動 | |
まとめ
正常な案件とクレーム、クレームとカスハラについて、境界線や判断基準は多くの企業さまが迷われるポイントです。本コラムを参考に、自社の判断基準を明確化し、マニュアルにも組み込んで、ひとりひとりの従業員・スタッフが迷わないようにしていただければ幸いです。
なお、悪質クレームやカスハラへの対応においては、マニュアルに組み込んだとしても、威圧的に怒鳴り散らされ暴力を振るわれるんじゃないかと思われる恐怖の中、適切に判断をし、マニュアル通りのセリフ・対応をするのは困難です。そのため、マニュアル化しただけでなく、それを現場の業務に当てはめ、スムーズに対応できるように研修やトレーニングをして行くことが重要です。
上記のような導入についてご相談を希望の場合は、ぜひお気軽に下記からご連絡下さい。