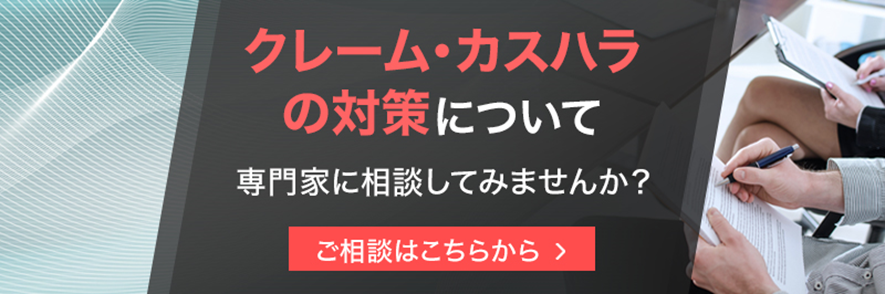クレーム対応 | 上手い人はやっている、基本的な対応フローの解説

全国で店舗展開しているある大手の印刷会社に印刷物を受け取りに行った際(念のため、キンコーズ様ではありません)、以下のようなやり取りを目撃しました。
- お客様:「これ、電話で「全部で19種類の資料が2部あるんだけど、すぐに確認して持って帰りたいから、一部ずつまとめておいて欲しい」って伝えたけれど、なんで個包装になっているんですか?」
- 従業員:さぁ、私には分かりかねます。とりあえず、資料に問題が無ければ、お受け取りのサインをお願いします(と言って受領証を差し出す)
- お客様:「ん? 中身の確認も確認しないでサインしろって事ですか?」
- 従業員:でしたら、お客様確認していただいても結構ですが。
- お客様:「どうやって確認するんですか? っていうか、その時間はどうするんですか?」
- 従業員:今ここで、お手元の商品を開いて確認いただければ、、、
- お客様:「さっきの話し聞いていました? 私は「すぐに確認して持って帰りたいから、一部ずつまとめておいて欲しい」って伝えたんですよ。つまり急いでる訳で、どこに個包装を外す時間があるんですかね?」
- 従業員:ですが、後で「受け取っていない」と言われても困るので、規程上、受領証にサインを頂くようになっておりまして、、、
- お客様:「それはお前らの都合だろ! 中身も見ねーでサインして、後でページが飛んでいましたってなったら、誰がどう責任取ってくれるんだ?」
- 従業員:それは、お知らせいただければ後からでも追加で印刷いたします。
- お客様:「揚げ足取るな馬鹿野郎! この資料はこの後今日中に、虎ノ門の弁護士に確認を取って、千葉の裁判所まで持参しなきゃいけねぇー大事な物だから、「後から追加」なんてできる訳ねぇーだろ!」
- 従業員:では、確認はしないで良い、ということでしょうか?
- お客様:「喧嘩売ってるのかコラ! 注文したものがその通りに出来上がるなんて基本中の基本だろ!! てめぇーじゃ話しにならねーから店長呼んで来い!」
- 従業員:そのような態度はカスハラなので止めて下さい!
- お客様:「うるせぇーよ! んじゃ、頼んだものがその通りに出て来ねぇーのに、サインを強要されるのは何ハラだオィ? 店長の意見を聞きてぇーから今すぐに呼んで来い馬鹿野郎!」
このやり取りの最後の部分だけを聞いて、「カスハラ」だと言うかたもいるかもしれません。
実際、対策本の中には「侮辱的な言動はカスハラ」と書いているものもあります。しかし、本件はすぐ隣りで聴いていた感想として、ちゃんと対応していれば全く揉める必要が無いように思えてならず、クレーム対応・カスハラ対応におけるよくある問題点が詰まっていると感じました。
確かに、企業や組織、そこで働く従業員に害をなす様な悪質なクレームやカスハラに対しては、組織的にしっかり対策して行くことが重要です。しかし、どのような対策であっても、揉める前に鎮火できるのであればそれがベストであり、そのためには、一人ひとりの従業員が適切に対応できるように、クレーム対応の基本的なフローや対応手順を整理することが重要です。
そこで今回は、お客様のご不満を初期段階で鎮火し、悪質クレームやカスハラに発展させず、反対に顧客満足の向上に繋げるための基本的な流れ・対応手順について、解説をいたします。
クレーム対応 | 上手い人はやっている、基本的な対応フローの解説
カスハラに発展させない、クレーム対応の基本的な流れ
冒頭のクレームの発端を端的に言えば、「お客様の注文通りに対応されていない」ことに尽きます。そうであれば、お客様が爆発した原因は以下の6点に整理ができます。
- 真摯な謝辞(感謝の言葉)や謝罪(お詫びの言葉)が無い
- お客様のお話しを傾聴していない
- 事実関係の確認をしてない
- 心情や真のニーズを理解しようとしていない
- 解決策を提示していない
- 企業の都合を優先している
つまり、発端は商品・サービスの不備でしたが、お客様が爆発することになった原因は従業員の対応不備です。
このように言えば、従業員の中には「そこまで求められても困る」と言う人もいます。
しかし、上記は決して、「従業員の責任だ」と言っている訳ではありません。むしろ、商品やサービスの不備を炎上させず、しっかりと解決し、従業員が余計な揉め事に巻き込まれないような顧客対応の手順を教育することは、明確に企業の責任です。そしてまた、それによりカスハラに発展せずお客様の満足度を確保することができれば、企業にとっても大きなメリットになります。
まず、真摯にお詫びする
お客様がお怒りの際、最初に行うべき行為は「お詫び」です。
時折、後で責任問題になるからと言って、事実関係が明らかになるまでは頑として謝罪しないという人もいますが、お勧めできません。そのような対応をしたらお客様の温度感は高まる一方ですし、僅かでも自社に非があった時に大炎上します。
別なコラムで詳述した通り、謝罪したからと言ってそれが即、責任を認めたことになることは通常ありません。ですから、企業側に責任があるか否か分からず、仮にお客様の誤解と思われるような場合であったとしても、心情に対し真摯にお詫びすることが、その後の対応から炎上リスクを排すことに繋がります。冒頭の例であれば、まずは「申し訳ありません」と速やかにお詫びしたうえで、例えば「こちらにその経緯が伝わっていなかったようです」など、その時点で回答できる範囲を回答しましょう。
お客様のお話しを傾聴する
お客様がお怒りの際、すぐに解決策を伝えようとしたり、または、自らに責任が無いことや正当性を伝えるために言い訳を伝えようとする人がいるが、これもお勧めできません。
企業内部の従業員・スタッフと違い、お客様は必ずしも正しい情報を持っているとは限りませんし、理路整然と説明できる方ばかりでもありません。そのため、お客様のお話しに口を挟まず、まずは何が起こったのか、どのように希望されているのか、丁寧に聴き取って行く必要があります。冒頭の例であれば、初っ端で依頼と違うと明確に指摘されていましたが、これをスルーして受領証へのサインを求めた結果、お客様に同じことを二度言わせて炎上への一因となりました。ですから、受領証へのサインを依頼する前に、お客様が指摘されたことに対し「大変恐れ入りますが、具体的にどのようなやり取りがあったか、教えて頂けますでしょうか」など説明を促す質問をするのも一法です。
【参考記事】
傾聴については以下コラムで詳しく解説しています。
正当なクレームをCS向上に変える! | プロが教える、傾聴のポイント10選
事実関係を確認する
前段で、解決策や正当性を伝えるための説明を急がない、と解説しました。これは、その大前提として事実関係を適切に把握していなければ、それらが全て的外れなものになる可能性が大だからです。そのため、基本は5W2H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように、いくらで)を意識しながら丁寧に確認して行きます。
一方、既にご不満をお持ちのお客様の場合、企業にとっては説明いただかなければ分からないことでも、お客様がメリットや意義を感じなければ、「なんでわざわざ説明してやらなきゃいけないんだ!? お前らで確認しろ!」と火に油となることもあります。従って、まず“この人はちゃんと聴こうとしている”と分かってもらうことが大前提ですが、これに加え、「もしかしたら今からでもご提案できることがあるかもしれませんので」など、説明を求める理由やメリットを提示できるならそうしましょう。
上記の基本手順は、商材や業界、組織特性などによって変わることも多いため、自社の実態に合わせた適切な流れを確立して行くことが極めて重要です。具体的には、まずは自社にどのような顧客接点があり、どのような業務・対応をしており、どのようなリスクがあるかを把握したうえで、それぞれのリスクが顕在化した場合の具体的な対応手順を整理して行きます。
上記のような対応について、一から自社で構築しようとする企業からよく聞く失敗例は、最初は顧客視点を念頭に置いていていたけど、途中から次第に社内の理論が優先されてしまって、現場感のない絵に描いた餅のような対応手順・対応フローになってしまった、といったものです。
もし、自社内で十分な経験が無い、場合には、特に初期段階においては、客観的な立場から助言ができる専門家の支援を受けることを強くお勧めします。お近くにそういった専門家がいない場合は、当社でもご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
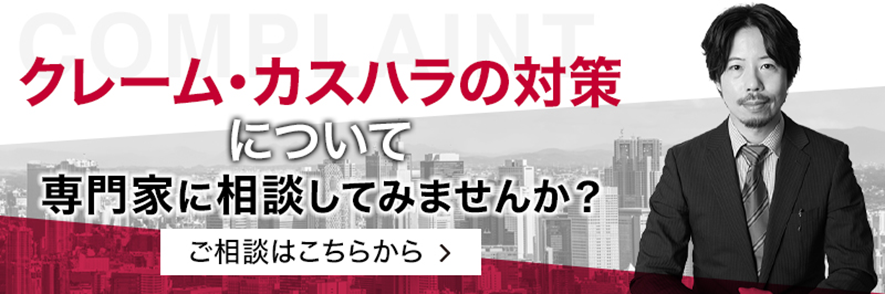
心情を理解し、真のニーズを理解する
冒頭の例であれば、お客様は「すぐに確認して持って帰りたいから」と仰っています。また、その後に「この資料はこの後今日中に、虎ノ門の弁護士に確認を取って、千葉の裁判所まで持参しなきゃいけねぇー大事な物だから、「後から追加」なんてできる訳ねぇーだろ!」とも仰っています。この時のお客様の言葉遣いが乱暴だと言えばそうかもしれませんが、企業として、正規の手続きで受け対価を受けと他注文に対応できず、上記のようにわざわざお伝えいただいたニーズをスルーしてしまっていることも大きな問題です。
前段で事実関係を確認したら、次は、お客様はなぜそう感じたのか、なぜお怒りなのか、その心情を理解し、真のニーズを理解するように努めましょう。そして、自分がどのように理解しているか、具体的な言葉にして伝え、お客様に受け入れてもらうことができれば、対峙し議論を戦わせる関係から、同じ側に立って共に解決を目指す関係に変化する可能性があります。
とはいっても、解決を急ぐ余り「要するに●●だったんですよね」などと、安易に話しをまとめようとしていると思われると、ますます大炎上することになりかねません。だからこそ、言葉にして伝える前の段階で聞いて、聴いて、更に訊いて、相手の心情を十分に理解してから言語化することが重要です。
再び冒頭の例であれば、「お急ぎで、しかもミスが許されない重要な書類だったからこそ、当社にお任せいただいたのですね」と訊きつつ、「ご信頼いただいたにも拘らず、個包装を外すようなお手間をかけたうえ、内容の確認もできずご不安を与えてしまい、本当に申し訳ありませんでした」などと寄り添い受け止めることが考えられます。
解決策を提示する
冒頭の例であれば、例えば、スタッフが手分けして個包装を外し一部ずつに分けて、お客様が内容を確認しやすいようにしてあげることが、その時点における最良の解決策だったはずです。なぜそれをしなかったのか分かりませんが、人員的に不可能な状況ではなかったのであれば、やはり、お客様が注文した通りに仕上がっていなかった訳ですから、何らかの解決策や代替案の提示はすべきでした。注文通りに仕上がらず、代替案も提示されなかったのであれば、お客様がお怒りになるのも止むを得なかったでしょう。
ポイントは、十分に傾聴し、事実関係や心情・真のニーズを十分に把握してから、解決策を提示する、ということであり、そのために今回のステップでは5つ目となっています。ここで解決策を提示することに対し、こんなに後になってから解決策なの? と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、クレームに発展しているということは、既にお客様は感情を害しているということです。そのため、提示した解決策が的を射たものであれば良いですが、そうで無ければ「そんなことは求めて無い!」と更なる炎上を招くことになりかねませんし、的を射た解決策だったとしても、「だけどあいつの態度は許せない」と心情的な不満が残りかねません。そのため、解決策の提示を急ぎ過ぎないよう注意しましょう。
企業の都合は問題解決の後にする
冒頭の例で言えば、受領証へのサインです。お客様が「注文通りでは無い」「中身を確認できない」と言っている訳ですから、その状態でなお、受領証にサインを求めることは企業の都合でしかありません。
もちろん、企業としては必要だったのだと思います。しかし、そうであったとしても、それをこの段階で確認するのは、自分が困っていること・迷惑を被っていることよりも、企業の都合を優先している、と思われても止むを得ないでしょう。
そう思われないためにも、やはり、まずはお客様の問題を解決し、解決してから企業側の依頼などをして行くべきです。
最後にもう一度、謝罪(お詫び)と謝辞(お礼)を伝える
解決策が奏功したとしても、問題自体が起こらなかったことになる訳ではありません。そのため、その点をしっかりケアすることで、事実上「解決した」とするとともに、顧客満足度向上の機会として行きます。
冒頭の例であれば、「ご要望通り対応できず、余計なお時間を取らせたこと、本当に申し訳ありませんでした。また、私どもの不手際にも関わらず、ご丁寧に経緯を教えていただき、ありがとうございました。今回の件は社内でも必ず再発防止策を講じますので、お許しいただけるのであればぜひまたご利用くださいませ」といったトークが考えられます。
まとめ
クレーム対応(特にハードクレームや悪質クレームへの対応)においては、「こう対応すれば良い」と頭で分かっていることと、激しく怒鳴り散らす相手を前に、「下手をしたら殴られるかも」と思いながら実際に対応できることの間には、雲泥の差があります。また、相手も一様ではありませんから、プレッシャーのかかるクレーム対応の場面において、その場の機転で必要なセリフを淀みなく伝えることは極めて困難です。
そのため当社では、今回のようなクレームへの対応フローを現場に定着させるためには、マニュアルを作成するとともに、具体的な場面に基づいた臨場感のある研修やトレーニングを行うことを推奨しています。
上記のような研修やトレーニングについて、専門家の支援をご希望の場合は、ぜひお気軽にご相談いただければ幸いです。