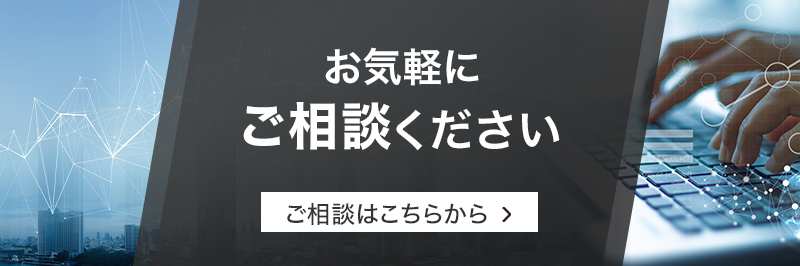顧客満足と顧客ロイヤルティの違いと、ロイヤルカスタマーを知る5つの質問
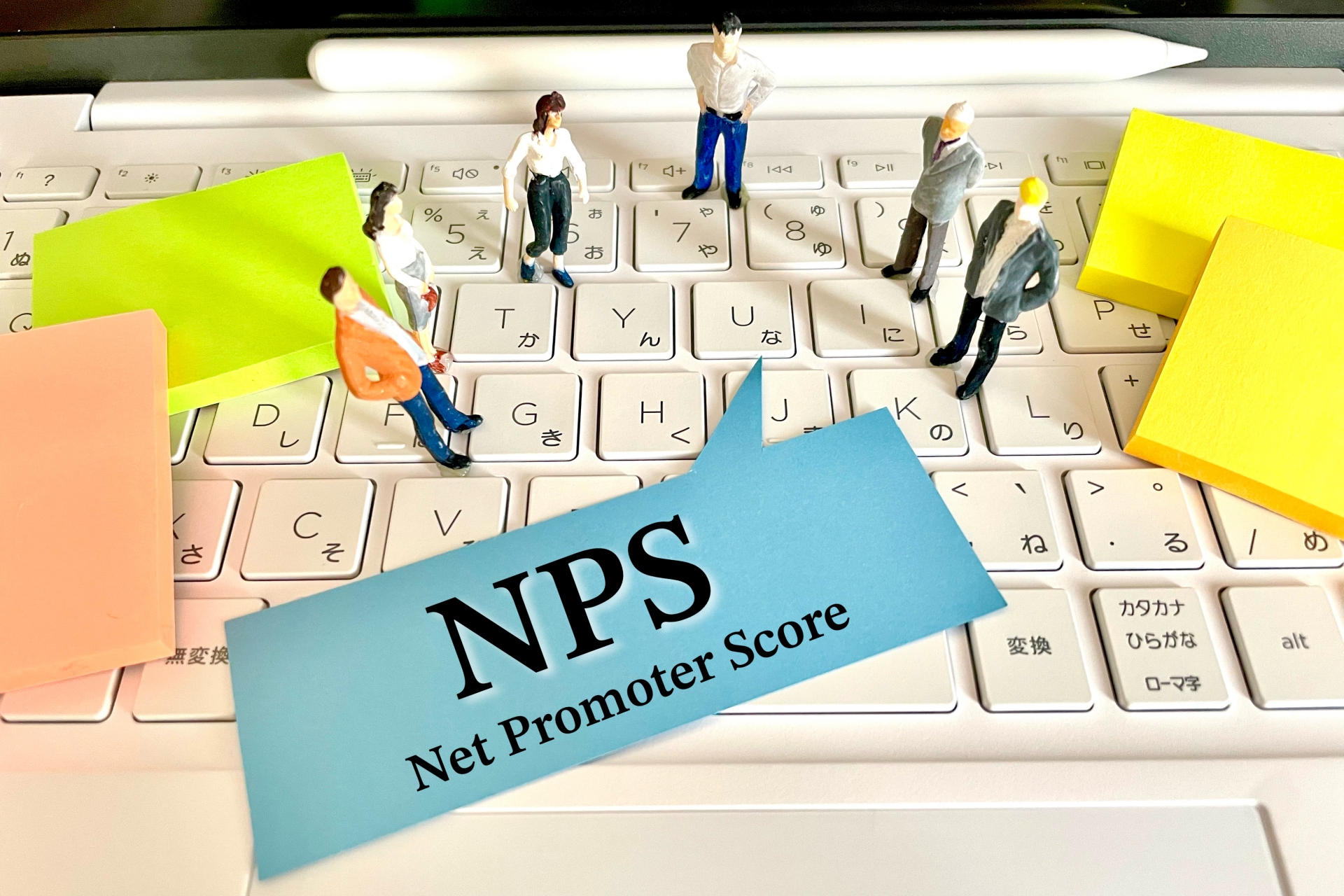
「あなたの会社のロイヤルカスタマーを教えて下さい」と訊くと、多くの方が、「売上上位のお客様です。」「当社は、上位20%のお客様が売上の8割を占めています」といった回答をします。しかし、売上上位のお客様がその企業を心から愛し、心から満足しているようなロイヤルカスタマーであるかというと、必ずしもそうではありません。
実際、埼玉県東部のあるタクシー会社では、長年、地元の固定客に支えられ堅調な業績を維持して来ましたが、利用者に対し顧客ロイヤルティを調査したところ、単に他にタクシー会社が無かったからというだけであり、実際のロイヤルティは低水準ということがありました。このような状態でもし、地域内に競合タクシー会社ができ、迎車料無料やタクシーチケットの割引などの強いキャンペーンをされたら、一気に売上の大半が流出してしまうことになります。
「お金はお金、どんなお金でも色は無い」と言いますが、顧客ロイヤルティの観点からは、明確に『良い売上』と『悪い売上』があります。『良い売上』とは、お客様の課題を解決し(または「解決できる」と思ってもらうことで)、お客様から喜んで対価を払ってもらうことによる売上です。反対に『悪い売上』とは、お客様の納得感が薄いばかりか、時には反感を持ちながら対価を払うような売上です。「嫌なら買わなきゃ良いだけだから、『悪い売上』なんて無いし、あっても顧客の責任」といった意見もありますが、例えば、代替品が無い、多額の解約金がかかる、変更手続きが複雑で面倒、といった理由で止むを得なく使っている商品やサービスは悪い売上に他なりません。このような売上は、顧客は利用しながらも自社への不満を募らせ、より良い競合を探し、周囲に自社への悪評を広げる可能性さえあります。
もちろん、『悪い売上』を積極的に排除する必要はありませんが、重要なことは、自社に対する顧客の評価を正しく把握し、『良い売上』を増やすための努力をすることです。
そこで今回は、顧客満足と顧客ロイヤルティの違いを知り、自社に合った指標を選び、それを高めていくための活動について、分かりやすく解説します。
顧客満足と顧客ロイヤルティの違いと、ロイヤルカスタマーを知る5つの質問
「顧客満足」と「顧客ロイヤルティ」の違い
「顧客満足」と「顧客ロイヤルティ」は同じような文脈で使われることが多く、意味合いもよく似ていますが、両者は同じものではありません。最初に両者の共通点から伝えると、以下の2点が挙げられます。
- 自社に対するお客様のポジティブな感情の度合いを示す
- 必ずしも売上上位客を指すものではない
これを踏まえて両者の違いを挙げると、以下のように整理できると考えます。
「顧客満足度」とは
日本工業規格 JIS Q 9000:2015『品質マネジメントシステム−基本及び用語』では、以下のように定義しています。
| 顧客満足(customer satisfaction) 顧客(3.2.4)の期待が満たされている程度に関する顧客の受け止め方。 |
「顧客ロイヤルティ」とは
「Loyalty(ロイヤルティ)」は、英語で「忠誠心」「忠実」「愛国心」などの意味があります。
ビジネスシーンでは様々な定義・考え方がありますが、当社では、以下のように定義しております。
| 他社の誘いに乗らず、自社のブランドに愛着を持ち、好んで継続的に購入してくれ、第三者にもお勧めをしてくれること。 |
両者の違いは「行動への結び付き」の度合い
両者の最も大きな違いは、行動にどの程度結び付いているかです。「顧客満足度」は個々の期待をどの程度満たしているかを示す指標であり、必ずしも実際の行動と結び付けるものではありません。それに対し「顧客ロイヤルティ」は、ブランド全体に対する愛着であり、単なる満足を超え、購入や第三者への推奨など実際の行動に結び付く指標です。
そのため、顧客満足度が低ければ、単にお客様に選ばれなくなるだけですが、顧客ロイヤルティは行動に結び付くので、マイナスの場合は積極的に嫌い悪い口コミやクレームをつけられる可能性があることにも注意が必要です。
前述の通り、両者には共通点があり、実務上でも同じ文脈で使われることが多いので、言葉を厳密に分けることにはあまり意味がありません。しかし、今回は「行動への結び付き」を強く意識するため、特に注記が無い限り「顧客ロイヤルティ」を優先します。
目標設定では、売上や利益と同等以上にロイヤルティが重要
ロイヤルカスタマーの割合が多いと、1人当たりの購入額が増えるため、売上の増加が見込めます。また、ポジティブな情報の紹介や口コミなどにより新規顧客の獲得や既存顧客の離反防止にもつながります。
一般的に人は誰かにその商品やサービスを紹介するとき、全く興味の無さそうな相手にも無差別に紹介したりはしません。その商品やサービスを気に入ってくれそうな相手を選び、優れている点や気に入っている点を魅力的に伝えてくれるため、紹介の時点から他の見込み顧客より成約率が高く、ロイヤルカスタマーになってくれる可能性も高まります。また、商品やサービスに対する理解度そのものが高いため、問い合わせ対応コストの削減にもつながります。
「色んな指標も結局は売上や利益に繋がるから、最初からそっちを目標にする」は危険
顧客満足やロイヤルティ向上の重要性について説明すると、「ロイヤルティも結局は売上や利益に繋がるから、最初から売上や利益をKGI(重要目的達成指標:Key Goal Indicator)にした方が合理的では?」「結局、顧客ロイヤルティが低いままでは長期的に売上・利益を得ることはできないのだから、売上や利益が確保できているということは、顧客ロイヤルティが高いということでは?」といった質問をされる方がいらっしゃいます。
しかし、そのように考えることは、以下の理由から危険と考えます。
人の行動は、遠い目的よりも目先の目標に最適化される
本来は目的の実現度を測るために目標があるにもかかわらず、いつしか、目標の達成が最優先となり、そのためなら目的をも逸脱するといったことはよくある光景です。
例えば、売上の確保だけが目的になり、お客様の課題やニーズを無視して(理解しようとせずに)、リスクやデメリットを隠したまま良いことしか言わない企業や、際限無い値引き合戦に陥っている企業は、枚挙にいとまがありません。それらは、短期的には売上に繋がることもあるかもしれませんが、ロイヤルカスタマーの育成には全く寄与せず、むしろ、冒頭で説明した『悪い売上』であることは明らかです。
売上や利益を目標にすることは、『悪い売上』に結び付く
ロイヤルカスタマーを育成し、『良い売上』を作るためには、自社の商品やサービスを好んでくれるお客様を理解し、そのお客様に価値を提供し、そのことに対し満足したお客様が自社に喜んで対価を払ってもらう関係を作ることです。対価=売上なので、売上はもちろん重要ではありますが、それだけをKGIにしてしまえばプロセスが軽視されてしまい、『悪い売上』を求める悪循環に繋がります。
顧客ロイヤルティを目標にすることのメリット
目標設定では、売上や利益よりも顧客ロイヤルティを優先すべきとお伝えしておりますが、両者は相反する指標ではありません。具体的には、顧客ロイヤルティを目標にすることには、以下のようなメリットがあります。
『良い売上』との連動性がある
前述の取り、顧客ロイヤルティとは以下のように定義されるものであり、この指標が高いお客様からの売上は、まさに、『良い売上』そのものです。
| 他社の誘いに乗らず、自社のブランドに愛着を持ち、好んで継続的に購入してくれ、第三者にもお勧めをしてくれること。 |
他社との比較がしやすい
顧客ロイヤルティを計測する代表的な指標であるNPSは、以下のステップで算出します。
| ① お客様に「○○をご家族や親しいご友人にお勧めする可能性はどの程度あるか、0~10で教えて下さい」と質問する。 ② 9~10を「推奨者」、7~8を「中立者」、0~6を「批判者」として集計する。 ③ 推奨者の割合 - 批判者の割合 = NPS |
上記の算出方法は業種や業界を問わず、公式として決まっています。
そのため、自社内で部署や時期が変わっても同じ条件で比較できるだけでなく、手間や費用は少々かかりますが、他社のNPSとも同じ条件で比較することができます。
NPSは推奨度を質問することで自然と他社比較の視点が入り、収益性との相関度も高まります。また、推奨先を「家族や親しい友人」とすることで、回答に対し真剣さと責任感が生まれ、お客様の未来の行動とも整合性が高まります。このNPSが潜在的な競合よりも低い場合には、早急にその原因を調べ、解消する必要があります。
顧客ロイヤルティの計測は、それ自体がお客様にとってCX(顧客体験:Customer Experience)であり、適切に対応できなければ以下のような三重苦に陥ります。
- そもそもデータが集まらない
- データの収集プロセス自体がお客様の不満度を高める
- 苦労してデータを集めても、内容が薄かったりノウハウが不足していたりで、改善に結び付かない
自社で顧客満足度や顧客ロイヤルティの計測をしたことが無い場合は、設計段階では専門家の力を借りることを強くお勧めします。もし、お近くに専門家がいないばあいには、当社でも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
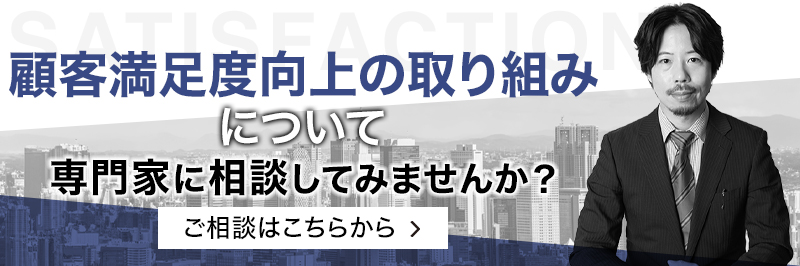
ロイヤルカスタマーを知る簡単な質問
NPSは有効な指標です。しかし、スコアを把握するだけでは、意味のある改善活動に結び付けることは困難です。そのため、以下のようなポイントを押さえた質問をすることで、顧客ロイヤルティに影響を及ぼす要素を把握します。
効果的な質問をする
商材によって、例えばアパレル商材やB to Bの場合には、ストレートに「○○をご家族や親しいご友人にお勧めする可能性はどの程度あるか、0~10で教えて下さい」と質問するだけでは、周囲と被るのを嫌がって低めの推奨意向を応えられてしまい、内心のロイヤルティがNPSに表れにくくなる場合があります。
そういった場合、アパレル商材の場合は「別な学校の親しい友人への推奨可能性」としたり、B to Bの場合には「家族や友人への推奨可能性」ではなく「同じ課題を抱えている同僚」としたりするなど、自社に合った効果的な質問に調整します。
適切なタイミングで質問する
多くのブランドにとって、購入や契約の直後と、事故やトラブルが起きた直後では、NPSに大きな差が生じます。そのため、実際に計測する前に、まず自社にとって最も重要な顧客評価はどのタイミングのものなのかを十分に検討することが必要です。
なお、可能であれば、購入や契約の直後、年次等での定点観測、事故やトラブルが起きた直後などそれぞれのタイミングで計測するのが望ましいですが、上述の通り、顧客ロイヤルティの計測自体もお客様にとって顧客体験の一部なので、頻度が増え過ぎると不満足に繋がることには注意が必要です。
適切な対象に対して質問する
ブランド全体に対するNPS評価と、商品やサービスに対するNPS評価、担当者個人に対するNPS評価では、それぞれ意味合いが異なります。商材によっては明確に分け難い場合もありますが、反対に、安価な汎用品の場合には、商品そのものだけでなく、提供プロセスや担当者についてのNPSも把握することで、顧客ロイヤルティを向上するヒントが見つかる場合があります。
スコアを計測するだけでなく、評価理由も把握する
改善活動においては、NPSのスコアだけでなく、なぜ高いのか(または、なぜ低いのか)、その理由を把握することが極めて重要です。そのため、アンケートなどを実施する際には、必ず理由欄を設けましょう。
なお、理由欄はできれば自由回答が望ましいですが、集計が困難な場合などは、最初は自由欄でサンプルテストを行い、一定の傾向を把握したうえでそれらを選択肢するなどし、効率化を目指します。
定量的な情報だけで判断せず、定性的な情報も活用する
顧客ロイヤルティは、お客様がそのブランドに対し心から信頼し、深い愛着を持っている状態を指します。しかし、NPSをはじめとした様々な指標は、いずれも、お客様の過去の経験や自覚しているニーズなど、顕在化した情報に基づいたものです。そのため、それ以上の大きなイノベーションには結びつきにくいという特性があります。
この壁を打ち破るためには、お客様自身がまだ気付いていない潜在的なニーズや将来に対する課題感など定性的な情報に対する深い洞察が必要です。そのため、スコアを把握するだけでなく、行動観察やインタビューなどを併用することで、顧客インサイトを理解することが不可欠です。
NPS改善のための注意点
NPSは有効な指標ですが、同じようにNPSが低い場合でも、批判者が多い場合と中立者が多い場合では、解消のためのアプローチが異なることには注意が必要です。
批判者が多い場合(「推奨割合30% - 批判割合50% = NPS▲20%」のような場合)
このような場合、端的に言えば、そもそものターゲティングが間違っているにも関わらず、お客様のニーズを無視した強引な売り込みで『悪い売上』を作っている可能性があります。
そのため解消方法は、批判者からの売上を積極的に放棄する必要はありませんが、前述のように目標設定やターゲティングを修正し、お客様のニーズを踏まえたアプローチをしていくことが重要となります。
中立者が多い場合(「推奨割合10% - 批判割合30% = NPS▲20%」のような場合)
このような場合、端的に言えば、自社ブランドの優れた点やニーズに合致している点が、60%を占める中立者に伝わっていない可能性があります。
そのため解決方法は、既存顧客との丁寧なコミュニケーションが基本方針となります。もちろん、60%の中には潜在的な批判者もいるかもしれませんが、大きな不満を持たず継続利用しているお客様も多いはずです。後者のお客様に対し丁寧に価値を伝え、中立者から推奨者に育成していくことが極めて重要です。
まとめ
自社の顧客ロイヤルティを知ることは、企業活動にとって極めて重要です。商品やサービスだけでなく、従業員の接客、広告、マーケティングなど、あらゆる活動に対し「その結果、お客様はどの程度の愛着を持ってくれているのか?」を把握することは、適切な改善活動のスタートラインです。また、自社に対する顧客ロイヤルティが低下して来るということは、潜在的な不満を持ったお客様が増えている可能性があり、なにかの拍子に、大きなクレームやカスハラに繋がる可能性もあります。
当社では、クレームやカスハラへの対策とともに、個客満足度や顧客ロイヤルティを向上させることで、クレームやカスハラが起こりにくい体質にすることが重要と考えています。
自社の顧客満足度や顧客ロイヤルティに関する取り組みについて、専門家へのご相談を希望の方は、ぜひお気軽に下記からご連絡ください。