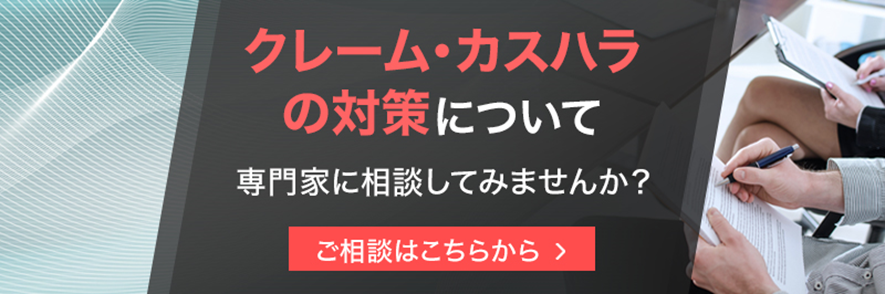【悪質クレーム・カスハラ対策】暴言、脅迫、暴力などの危険から従業員を守る

先日、遠方の仕事が終わって帰路につく途中、食事をとろうと駅ビルに入ったら、テナントの飲食店内に大きく、「カスハラは許さない!速やかに警察に通報します」などと書かれたポスターを見付けました。
確かに、明確なカスハラであって、差し迫った身の危険を感じるのであれば、速やかな通報は有効な対応ですし、そうするべきです。しかし、直接的な暴力など分かりやすい被害が伴わない場合や、こちらに一定の原因がある場合などには、警察への通報を躊躇してしまいがちです。実際、それが正しいかどうかは別として、相手には相手なりの理由があるので、状況の把握が不十分なまま毅然とした対応をしようとしても、相手の勢いに飲まれてしまいそうになってしまうこともあります。
一方、そのような状況に躊躇してしまい、漫然と対応を続けていると、どこかのタイミングで相手がヒートアップし、突如、暴力的な行為に及ぶといったこともあります。
そこで本コラムでは、適切に顧客対応をしながらも従業員を実害から守る対応のポイントについて、解説いたします。
【悪質クレーム・カスハラ対策】暴言、脅迫、暴力などの危険から従業員を守る
悪質クレームやカスハラの危険度レベル
カスハラの中でも、暴力行為は従業員の身に直接的な危害を及ぼす行為であり、特段に注意が必要です。
しかし、直接的な危害を回避するためには、暴力行為だけに気を付ければ良いのかと言うと、そういう訳ではありません。いわゆる「リピート型」や「時間拘束型」が、どちらかと言えば差し迫った危険に直結し難いのに対し、「暴言型」や「脅迫型」は、最初は身体的な暴力が伴わなくても、要求が通らなければ「暴力型」に発展したり、暴言や脅迫に対し従業員がやり返して加害者にもなってしまったりなど、大きなリスクがあります。そのため、暴言や脅迫の段階から適切に対処し、危険な暴力行為に発展しないようにすることが重要です。
具体的には、以下のような行為は、暴力に発展する可能性を念頭に置いて対応することをお勧めします。
暴言(大声、侮辱、人格否定などの言葉の暴力)
大声で怒鳴る場合だけでなく、「ブス」「ババァ」「ハゲじじい」など容姿に関する侮辱や、「無能なクズ野郎」などの人格否定も、厚生労働省『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』における「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動(精神的な攻撃)」暴言に該当する可能性があります。
脅し(暴力などを示唆して無理矢理要求に従わせようとする行為)
「ぶっ殺すぞ!」といった直接的な暴力行為だけでなく、「●をしなけりゃネットで晒してやる」といった発言も、厚生労働省『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』における「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動(精神的な攻撃または威圧的な言動)」に該当する可能性があります。
物に当たる(机を叩いたり、物を投げたり、壁を蹴ったりすることで威嚇する行為)
その「物」が相手自身の持ち物だったり、それが自分にぶつからなかったりしても、威嚇として行われたのであれば、厚生労働省『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』における「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動(威圧的な言動)」に該当する可能性があります。
暴力(殴る蹴るだけでなく、掴まれる、押される、唾を掛けられるなどの行為も該当)
「暴力があればすぐ警察を呼ぶから一番簡単」といった声を聞くことがありますが、相手が刃物を持っている可能性もあり、被害を受けてからでは取り返しがつきません
筆者は、勤務時代に600人近くいるコールセンターで朝礼をしている時、トラブルになっていたお客様が、スパナやカッターを持ったまま紛れ込んでいたことがありました。その時は、学生が大半のセンター内に作業服姿の中年男性がいたため、トラブルになる前に気付いて警備を呼べましたが(本人も雰囲気に呑まれて暴れられなかった模様)、一歩間違えば刃傷沙汰であり、背筋が冷たくなったことを覚えています。
最も重要なことは、暴力の実害を防ぐこと
前述の通り、カスハラの中でも暴力行為は特に警戒が必要であり、被害から従業員を守るためには、暴力を振るわれてから警察を呼ぶのではなく未然防止がベストです。そのための基本的な方向性は、『牽制』と『退避』の2つとなります。
以下、具体的に見て行きましょう。
暴力を振るわれないように予め牽制する
暴力を振るったらどうなるのか、以下のようなアプローチにより明示的に伝えることで、暴力行為を牽制し、相手が暴力を振るい難い状況を作ります。
- 「警察官立ち寄り所」のステッカーを入手し掲示する
- カスハラ対応ガイドラインを掲示する
- 具体例や警察への通報を明記したカスハラ対策ポスターを掲示する
- 監視カメラを設置する
- 警備員を配置する
具体的には、1は自社で用意したステッカーを所轄警察署の生活安全課に持ち込み、署長の承認を得れば提示できるとのことです。ただし、掲示したからといって警察の巡回が約束される訳では無いので、示威効果を狙うものです。
2と3は基本的には同じものであり、ガイドラインを作成した後、その内容から抜粋して目立つようなポスターを作成することが多いです。なお、ガイドラインはただ作るだけでなく、それに沿った内部体制を構築しなければ、顧客対応の前に従業員の間で形骸化してしまうことには、注意が必要です。
筆者の感覚では、上記のリストのうち最も簡単に導入できるのは1のステッカーであり、最も牽制効果が最も高いのは5の警備員の配置です。ただし、警備員はコスト負担も最も大きいので、4の監視カメラと併用することが多いです。
実務的には、まずは2~3を構築しながら4~5の必要性を検討し、重要なポイントに絞って導入するのがお勧めです。
クレームが発生した時点で速やかに本社にエスカレーションする
上記のような牽制をしてもなおクレームが発生し、必要な対応を誠実に行っても一向に納得いただけず、長期化が見込まれる場合は、以下の様にお伝えし速やかに本社にエスカレーションしてしまうことも一法です。
- ご要望については、店舗スタッフで対応できる範疇のお話しではございません。恐れ入りますが、本社から連絡をさせていただけないでしょうか。
- 申し訳ございませんが、店舗スタッフでは個別のご要望について回答することができません。大切なご要望なので、本社からちゃんと連絡させていただくようにお願いいたします。
ポイントは、早い段階で自分たちに権限が無いと伝え、「ここで脅したり殴ったりしても無駄だ」と思ってもらい、その後のカスハラや暴力行為の矛先を逸らすことです。
ただし、それでも納得しなかったり、逆上したりなどで、暴力を振るわれそうになる場合があります。そのような場合には以下の様に対応して行きます。
それでも暴力を振るわれそうになったら速やかに退避する
上記のように矛先を逸らしても、暴力を振るわれそうになることはあります。そのような場合には極力刺激しないように注意しながら、速やかにその場から退避しましょう。
手を出されても、極力、やり返さないようにしましょう。理不尽だと感じるかもしれませんが、相手は武器を持っているかもしれませんし、揉み合って怪我をさせたら、相互暴行になる可能性もあります。不当クレームやカスハラを相手に怪我をしたり、罪に問われたりすることになれば、これほど馬鹿らしいことはありません。
また、その場は格好良く取り押さえられても、そのことを恨んで付け狙われ、会社を出たところを突然襲われたりしたら、防ぐことは困難です。
そうならないようにするためのポイントは、以下の2点です。
- 相手を刺激しないこと
- 暴力を “振るわれそうになった時点” で速やかに退避すること
逆上して暴力を振るわれないように、刺激しないように気を付けるとともに、実際に暴力を振るわれる前に「上司を呼んで参ります」などと“言いながら”その場を立ち去ってしまいます。呼び止められても立ち止まる必要はありません。その場から立ち去った後は、上司や同僚を呼んで複数名で対応しても良いですし、危険を感じたのであれば、そのまま警備や警察に連絡しても良いです。
暴力を振るわれそうな相手に対しては、無理に対応しようとせず、眼前から速やかに立ち去ってしまうことを最優先にし、後は、組織としてのルールに沿って対処しましょう。
暴力行為は、発生してから慌てても、適切に対応することは困難です。
飽くまでも、暴力を振るわれそうになった場合など「緊急時」の対応なので、危険を回避することが最優先であり、難しい交渉などは必要ありません。しかし、そのためには「どのタイミングで何をするのか」が具体的に共有されていなければ、適切に対応することはできません。逆に言うと、様々な悪質クレームやカスハラの中でも、マニュアル化やトレーニングなどの効果が大きい領域でもあり、クレームやカスハラに対応する組織体制を構築する際は、その第一歩に適した領域でもあります。
上記のような緊急時対応を含めて、組織的に対応するため、専門家に相談してみたいという方は、下記よりお気軽にご相談くださいませ。
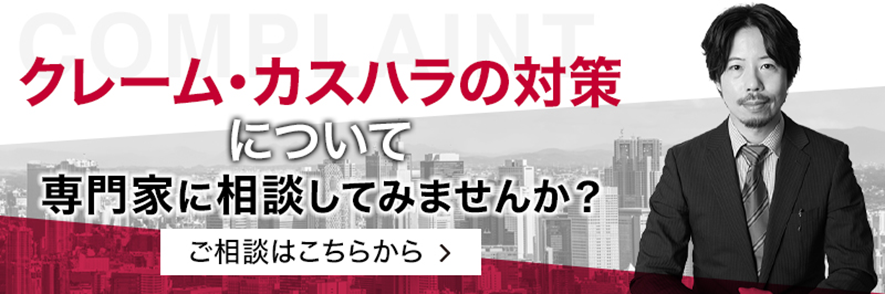
次に重要なのは、自分が加害者になってしまわないこと
相手が興奮して暴力を振るって来たとき、それを止めさせるため抑えようとして取っ組み合いになってしまったり、こちらも興奮して手を出してしまったりしたら、最悪の場合、相互暴行としてこちらも罪を問われることになります。そのため、自分が被害者にならないようにすることの次に重要なことは、自分が加害者にならないようにすることです。
こちらが何もしなくても被害者になってしまう可能性はありますが、こちらが何もしなければ加害者になることはありません。つまり、その点をしっかり理解していれるだけで、加害者になることは防げる可能性が高まります。そのため、冷静に対応することの大切さ、万が一手を出してしまった場合の社会的責任の大きさを伝えるなど、従業員教育の重要性は極めて大きいです。
大半は、暴力や刃傷沙汰の前に何らかの兆候がある
大半のクレーマーやカスハラ相手は、全く唐突に暴力を振るったり、ましてや刃傷沙汰を起こしたりはしません。例えば、2024/7/16に愛知県高浜市役所で男性が刃物を振り回した事件では、2年前から納税を巡るトラブルがあったと報じられています。
我々は人の心の中を読むことはできないので、目の前のお客様が暴力を振るおうとしているか否かを、外から見るだけで正確に判断することは困難です。しかし、既にトラブルになっていたり、それが長期間解決できずにいたりする場合などは、前述のような牽制をしたり、最寄りの警察署に相談したり、可能なら警備員を配置したりなど、予め対策を講じておいた方が無難です。自治体などで防犯講習などをしている場合には、参加しても良いでしょう。
また、そういったトラブルになっている相手が、前述のような暴言、脅し、物を叩くなどの行為をしたら、躊躇せず警察を呼ぶなど、毅然とした対応をすることも重要です。そうしなければ、次からは物を叩いたり脅したりすることのハードルが下がり、暴力にエスカレートしてしまいやすくなるので、前兆の段階で強く牽制しておきましょう。
ただし、必ずしも『 暴言 > 脅し > 物に当たる > 暴力 > 刃傷沙汰 』という順番に進む訳ではないことには、注意が必要です。そのため、危険を感じる場合には、例えば受付を少し高くしたり、机の奥行を長くしたり、咄嗟の場合の対応を訓練したり、といった対策を講じることを検討しましょう。
突発的な来社・訪問にも備える
暴力的な言動への対応が難しい理由の一つに、体制やノウハウが無い状況の中で突発的にトラブルが発生するため、現場のスタッフ・従業員に対応を強いられることがあります。そのため、突発的な来社や訪問に備えておくことも有効な対策です。この点は、前段で紹介したように本社にエスカレーションする場合にも、本社側で押さえておくべきポイントです。
別なコラムで詳しく説明しましたが、来社や訪問に対しては、以下のような対策が有効です。
- セキュリティカード認証システムの導入により外部からの侵入を物理的に遮断する。
- 入館受付時に手荷物をロッカーに入れてもらうことで武器の持ち込みを防ぐ。
- 録画可能な応接室を用意し重量物や突起物は置かないようにする。
なお、飲食店や小売店のような店舗ビジネスの場合は、上記のような対応が難しい場合もあります。しかし、その場合もバックオフィスの来客スペースに案内する際に手荷物を預かったり、複数名で対応したり、といった対応を心掛けましょう。
複数名で対応する場合も油断せず、予め役割分担を明確にしておく
厚生労働省のカスタマーハラスメント対策マニュアルや、市販のクレーム・カスハラ対策本などを見ると、一様に複数名での対応を推奨しています。しかし、複数名での対応は、実は、1人で対応する時よりも難しい場合があります。例えば、こちらが相手を取り囲むような状況になると逆上してかえって大声を出したりする人もいますし、相手も複数だった場合は、どこで小競り合いから掴み合いになるか分かりません。実際に、土下座事件として有名になったしまむら様の場合は、従業員の方は2名だったと報じられています。
こちらも、別なコラムで詳しく説明しましたが、複数名で対応する時には予め以下のような役割分担を決めておき、その役割に沿って機械的に行動することをお勧めします。
- お客様との対応をする役割
- 関係先に対し連絡する役割
- 記録を取る役割
まとめ
繰り返しになりますが、悪質クレームやカスハラに伴う乱暴行為に対しては、最も重要なことは日会社にならないことであり、次に重要なことは加害者にならないことです。そして、そのためには未然防止の重要な考え方が重要であり、ガイドラインやマニュアルの作成、従業員への研修など、事前準備を含めた、社内体制の構築が不可欠です。
上記の様なクレームやカスハラへの対策の仕組み作りについて、専門家にご相談を考えられている方は、当社でも承っておりますので、ぜひお気軽に下記からご連絡をいただければ幸いです。
【参考コラム】
【カスハラ対策】基本方針・ガイドラインの作成方法を3ステップで具体的に解説
使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説